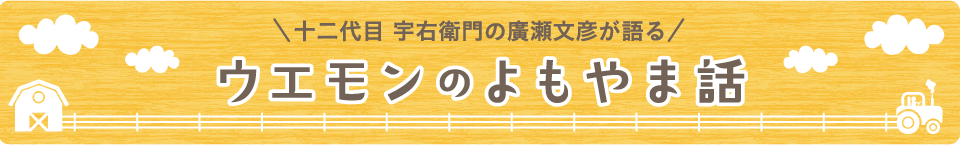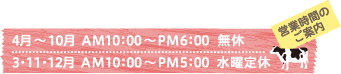第6回廣瀬家地蔵盆
予ねてから延期されていた廣瀬家の地蔵盆盆を、16日正午から同朋寺住職を招いて挙行した。



例年7月24日に実施していたが、家族眷属の安寧を願って地蔵盆を発願した老父が肺炎で立て続けに2度入院したため
8月16日に延期していた。
家族の心配を他所に、日常生活に戻っているので、老父母揃ってお詣りする事ができた。


孫も参加してくれた。
玉音放送.昭和20年(78年前)
終戦の詔書
朕(ちん)深ク世界ノ大勢ト帝国ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以て(もっ)テ時局
ヲ収拾セムト欲シ茲(ここ)二忠良ナル爾(なんじ)臣民ニ告グ
朕ハ帝国政府ヲシテ米英支蘇四国ニ対シ其(そ)ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セ
シメタリ
抑々(そもそも)帝国臣民ノ康寧(こうねい)ヲ図リ万邦共栄ノ楽ヲ偕(とも)
二スルハ皇祖皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ拳々(けんけん)措(お)カサル所曩(さき)
二米英ニ国ニ宣戦セル所以(ゆえん)モ亦(また)実ニ帝国ノ自存ト東亜ノ
安定トヲ庶幾スルニ出テ他国ノ主権ヲ排シ領土ヲ侵スカ如(ごと)キハ固(も
と)ヨリ朕カ志ニアラス然(しか)ルニ交戦已(すで)二四歳(しさい)ヲ閲
(けみ)シ朕カ陸海将兵ノ勇戦朕カ百僚有司ノ精励朕カ一億衆庶ノ奉公各々最善
ヲ尽セルニ拘(かかわ)ラス戦局必スシモ好転セス世界ノ大勢亦我ニ利アラス加
之(これにくわうるに)敵は新ニ残虐ナル爆弾ヲ使用シテ頻(しきり)二無辜ヲ
殺傷シ惨害ノ及フ所真ニ測ルヘカラザルニ至ル而(しか)モ尚交戦ヲ継続セムカ
終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招来スルノミナラス延(ひい)テ人類ノ文明ヲモ破却スヘ
シ斯(かく)ノ如クムハ朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子(せきし)ヲ保(ほ)シ皇祖皇宗
ノ神霊ニ謝セムヤ是(こ)レ朕カ帝国政府ヲシテ共同宣言ニ応セシムルニ至レル
所以ナリ
朕ハ帝国ト共ニ終始東亜ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ対シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得
ス帝国臣民ニシテ戦陣ニ死シ職域ニ殉シ非命ニ斃(たお)レタル者乃其ノ遺族ニ
想(おもい)ヲ致セハ五内(ごだい)為ニ裂ク且(かつ)戦傷ヲ負ヒ災禍ヲ蒙
(こうむ)リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ朕ノ深ク軫念(しんねん)スル
所ナリ惟(おも)フニ今後帝国ノ受クヘキ苦難は固ヨリ尋常ニアラス爾臣民ノ衷
情モ朕善ク之ヲ知ル然レトモ朕ハ時運ノ趨(おもむ)ク所堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難
キヲ忍ヒ以テ万世ノ為ニ太平ヲ開カント欲ス
朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚(しんい)シ常ニ爾臣民
ト共に在リ若シ夫(そ)レ情ノ激スル所濫(みだり)二事端(じたん)ヲ滋(しげ)
クシ或ハ同胞排擠(はいせい)互ニ時局ヲ乱リ為ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ
失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム宣(よろ)シク挙国一家子孫相伝へ確(かた)ク神
州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念(おも)ヒ総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ道義ヲ
篤クシ志操ヲ鞏(かた)クシ誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコ
トヲ期スヘシ爾臣民其レ克(よ)ク朕カ意ヲ体セヨ
祈る
病院の待合室で、待ち疲れた老父
1日でもと夫の長生きを願う老母
「親孝行 したい時には 親は無し」か!
父親の一時危篤を経験してからは、老父母にもいつかは終命の時は来ると悟らされた。
我々子ども達も、長生きしてくれと祈るばかり。
じゅうななつ⁉︎
カーラジオから「...こくれんがきめた じゅうななつのもくひょうぁあるよね...」
「あぁ、えすでぃじーずのことね」と、聞こえた二人の言葉に違和感を感じた。
普通の日本人なら、耳から入った言葉は頭の中で自動的に漢字に変換されて、
「...国連が決めた17つ(⁈)の目標が有るよね...」
「あぁ、SDGsの事ね」となっている筈だ。
この中で「17つ(じゅうななつ)」と言う言葉が引っかかってしまった。
日本語では、ものの数を一(ひとつ)、二(ふたつ)、三(みっつ)、四(よっつ)、......と数えて行き、
十では、(とうお)となり、それ以降は、「つ」は付けない。
「つ」を付けない代わりに「個」とか「本」とか助数詞をつけるのが正解だろう。
十一はじゅうひとつ、十二はじゅうふたつ、そして十六はじゅうむっつ、十七はじゅうななつ?
変じゃありませんか?
その通り!
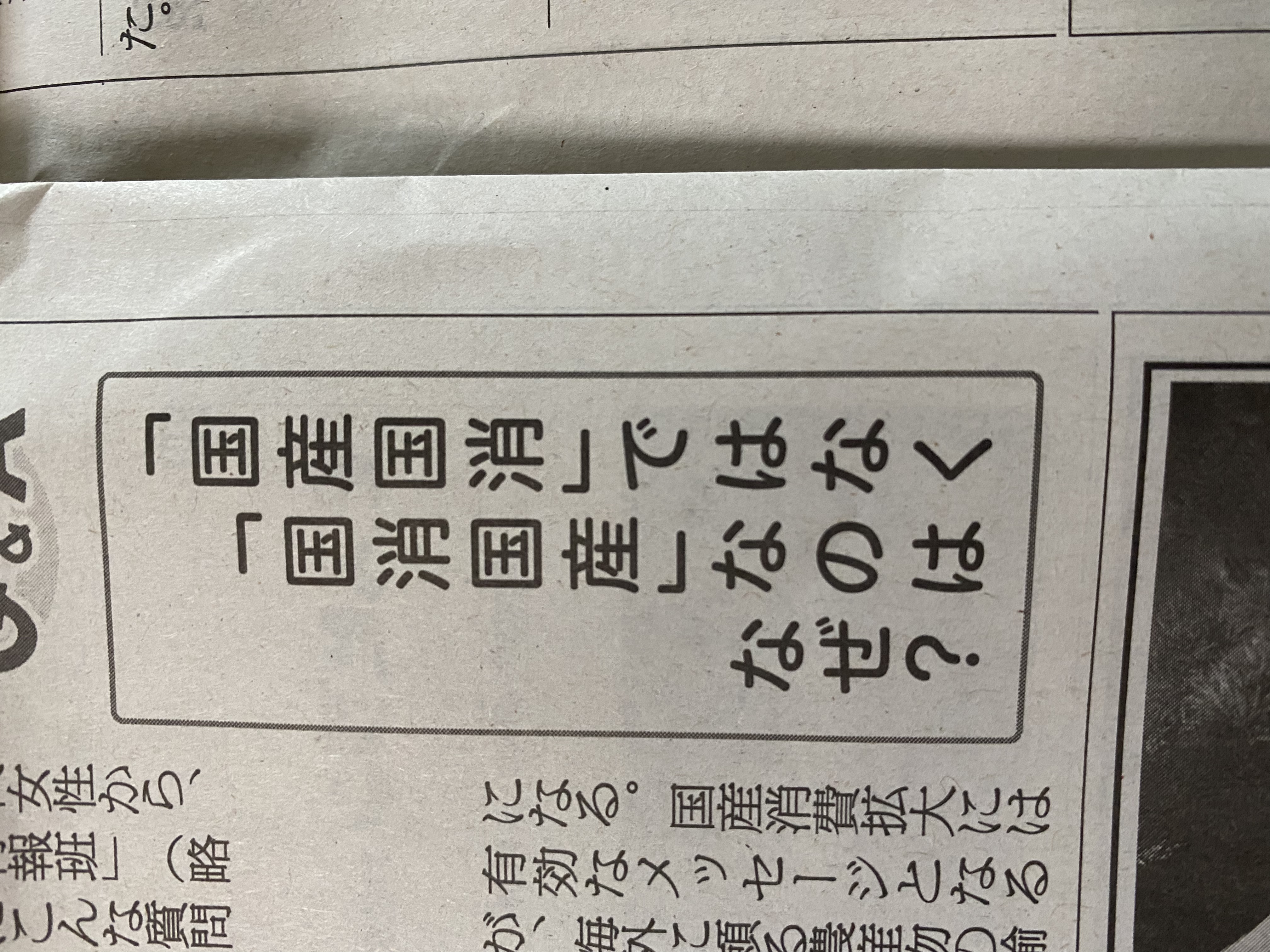
今日の業界紙三面の「のうとくQ&A」から
旧来から「地産地消」或いは「国産国消」と言われて久しいが、それは地域或いは自国で採れたものを
その地域、国で消費しようと言うもので、所謂「身土不二」と言う意味も含んでいる。
これに対して「国民が必要とし、消費する食料は、出来るだけ自国で生産する」と言う意味で、
食料自給の大切さを前面に出している。
2020年に食糧安全保障への危機感から、JA全中が提唱したのが「国消国産」だ。
このQ&Aでは、国民が必要とする食料を作り続けるには、その担い手である農業・農村を支えてもらい、
生産基盤を強化する事も重要になってくる。」
さて自分事だが、ずんずんと進んでいく生消の乖離に気付き、農業を守るには消費者と共に(共通理解)なければならないと思い始める。
30代半ばの頃だ。
そして農業者自ら「伝える」活動は農作業の一環と位置づけ、1991年(平成3年)から酪農教育ファーム活動を本格的に始めた。
その活動も34余年になるが、当初から消費者の国産食料に対する期待の大きさはヒシヒシと感じていた。