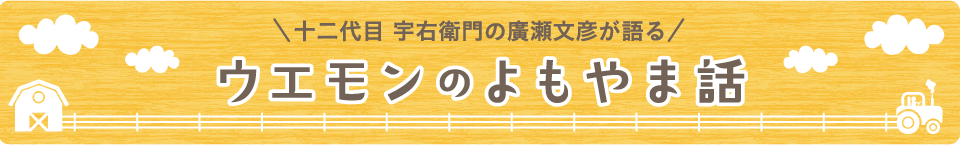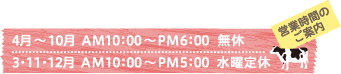ハナモモ
牛舎の敷地の一部には低木の生垣が有りますが、枝打ちをするなど手入れが行き届かず伸び放題。たわわになるほど花も付けられず、所謂「ザッシモナイ(美濃言葉か、散らかっているとか整理がされていない状態を言う)」状態です。
このレンギョウも日当たりの良い所は見事に咲いていますが、日陰になる部分は枝ばかり・・・・「全くザッシモナイ!」。
この生垣の半分はピンクの花をたわわにつける低木が占めています。
スタッフが通勤途中そのピンクの花をスマホで撮ってきて「どうです綺麗ですよね・・、ところでこれはなんという花なんですか?」。「えっ、名前?知らねえな、年を喰っているからといって何でも知っているわけないじゃん!」と反論。でもやはり年を伊達に喰っていと思われるのも片腹痛い!早速ネットで調べてみる(便利な時代だ)と"ハナモモ"だそうです。ピンクた白、白にピンクの斑入りのものなどがあるようです。しかしこれもザッシモナイ状態で満開にならず、恥ずかしい限りです。
でも満開になると「ハナモモ」お見事・・・
手入れをすればこうなるのです・・・・!
因みにこれは未だ蕾ですが「木瓜(ボケ)」です。
どうです?!春爛漫!百花繚乱!
御神木
 これ、ウエモンズハートの裏庭にあるスモモです。
これ、ウエモンズハートの裏庭にあるスモモです。
 この根元を見てください。幾星霜、風雪に耐えて来たのか自然界の厳しさを体現しているようです。私が物心付いた時にはすでに立派なスモモの木で、良く実を拾って食べたものです。私が生まれて64年。我が家が中札内から引っ越してきたのが昭和13年(1938)。そのときの前小作人から地上物件の引渡し確認書に「スモモの木」と載っているので78年前にはすでに地上物件として記載されるほどの木になっていたのです。樹齢は凡そ100年で我が家のご神木と言っても過言では無いでしょう。
この根元を見てください。幾星霜、風雪に耐えて来たのか自然界の厳しさを体現しているようです。私が物心付いた時にはすでに立派なスモモの木で、良く実を拾って食べたものです。私が生まれて64年。我が家が中札内から引っ越してきたのが昭和13年(1938)。そのときの前小作人から地上物件の引渡し確認書に「スモモの木」と載っているので78年前にはすでに地上物件として記載されるほどの木になっていたのです。樹齢は凡そ100年で我が家のご神木と言っても過言では無いでしょう。

 今年もこんなに綺麗に花を付け私達の目を楽しませてくれます。
今年もこんなに綺麗に花を付け私達の目を楽しませてくれます。
いよいよ、それともようやく?

 牛の飼料であるデントコーンの播種が始まりました。昨年は入院していたので2年ぶりの風景です。先ずは播種しないことには収穫もありえないので、今年もこの時期を迎えられたことに感謝です。
牛の飼料であるデントコーンの播種が始まりました。昨年は入院していたので2年ぶりの風景です。先ずは播種しないことには収穫もありえないので、今年もこの時期を迎えられたことに感謝です。
私のやっていた頃には大体5月の連休中にはコーンの播種は終了するように作業を進め、そして一日のんびり花見と称して妹家族も呼んでジンギスカンをやるのが恒例行事でした。一生懸命やっている息子にとっては不本意でしょうが、何でこんなに遅くなるんだ、と、ついつい比べてしまいます。近隣に一軒だけある酪農家"〇塚農場"さんといつも競うようにコーンの播種や牧草の収穫をしていたものでした。私が5月の1日~5日頃に播種し、〇塚さんは大体10日頃からの播種で今年もオレが早かった!なんて一人自己満足に浸っていました。しかし、植物の発芽の条件が"水・空気・温度"でその地温が有る程度上がってこないと勢い良く発芽してくれないんですね。結論から言うと10日も早く播種をしても発芽は数日しか違わないことが多かった様な気がします。ある年は作業が遅れ、畑を耕した翌日には播種をしましたそれから待つこと2週間経ってもまばらにしか発芽してきてはいないですか。どうした?種が腐った?分からず覆土を除けてみるとなんと大半の芽が下に向かって発芽し、途中から思い直したようにUの字状に地上に向かっているので発芽に時間を要していたようです。何故か?先ほどの発芽の三要素のうちの温度です。畑を耕起することを天地返しとも言うくらいで、反転した土の表面温度が充分に上がらないうちに播種をしたので芽が温かい方に向かって伸び始めたんですね。そのことがあって亡祖父種治が生前、「春畑を耕した後一週間は種を播かないほうがいいぞ・・・」って言っていたことを思い出しました。年寄りの言うことは良く聞いておくものだと痛感しました。

自分自身若い頃、自分では一生懸命作業を進めているつもりでも、事あるごとに父に「まだ〇〇しないのか」「いつまでそんなことやっているんだ!」と言われ続け、家を飛び出そうと思いつめる時代もありました。
もっと早く播種作業をやればいいのに「ようやくか」・・・・と思うか、「いよいよ」今年もこのシーズンを迎えられたかと感謝するか・・!心のありようです。
馬糞風
十勝の春の風物詩、馬糞風の到来です。
 見てください。500m先の農家住宅なども土ぼこりで殆ど見えません。
見てください。500m先の農家住宅なども土ぼこりで殆ど見えません。
 空は快晴の青空。地平線付近の我が家の建物群が土ぼこりで霞んで見えます。防風林の立木も強風に煽られ右方向にたなびいています。
空は快晴の青空。地平線付近の我が家の建物群が土ぼこりで霞んで見えます。防風林の立木も強風に煽られ右方向にたなびいています。
こんな中でも農作業は行われますが、口の中は"じゃりじゃり"。目は"シカシカ"。鼻の穴、耳の穴は真っ黒けになってしまいます。
明治から大正に掛けて開拓と称して樹木が伐採され、笹やスゲが刈り取られ、十勝が広大な農地に生まれ変わりました。それと共に火山灰土壌の土は春先の耕したままの無防備な状態では大風が吹くと土が飛ばされる現象が起きるようになりました。豆などを播種した後に大風が吹くと厚さ3~4㎝の覆土が全て吹き飛ばされ播種しなおしたり、その土が明渠を埋めてしまったり!と、例年のように春先の風害があったそうです。その先人達の知恵から十勝の風物詩"防風林"が生まれました。
昔は様々な物資の輸送手段の大半は馬車に頼っていました。その馬、出物、腫れ物ところ構わずで排気ガスならぬ馬糞があちこちに落ちていたそうです。その馬糞も春先の風で乾燥し風に飛ばされるくらいの強風、と言う意味で"馬糞風と言うんだ"と亡祖父が言っていました。
開墾着手
今日から例の耕作放棄地の抜根作業が始まった。
行って見てびっくり!重機が2台・・・。どうなってるの???。
奥の黄色い重機は今回私達が頼んだ佐々木畜産のものですが、手前のオレンジ色の2台の重機は直ぐ隣のコンクリート砕石業の㈱岩佐のもので、地主さんが頼んだものでした。
 画面右奥に見える黄色のタイヤショベルは息子が引っこ抜いた木を一箇所に集める作業をやっているところです。
画面右奥に見える黄色のタイヤショベルは息子が引っこ抜いた木を一箇所に集める作業をやっているところです。
最初、息子は一人で抜根作業をやるつもりでしたが、何日かかる事やら心配でしたが、大勢の皆様のご支援のお陰様で一日仕事で終わることが出来ほっとしているところです。
この後、ラウンドアップを散布し、今年のデントコーン栽培予定地に全て播種を終えた後、プラウイングし整地して播種と言う段取りでしょうか・・・・